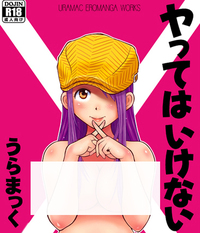2015年02月13日
第918話「モンハンキット組立塗装講座その②」の巻
モンハンキット組立塗装講座の続きです。
講座ってほど偉そうなものでもないですが。
今回は塗装のテクニックについてです。
WF会場内で「エアブラシ持ってないし、こんなの塗れない!」
みたいな声を何度も耳にしたのですが、自分はほぼエアブラシは
使いません。何故って掃除とメンテナンスがめんどくさいから。

例えばWSCプレゼン作品の作り起こしベースは、近所のDIYで
適当な赤と青と緑の缶スプレーを買ってきて、ばばっと吹いて、
あとは筆でプラカラーをぐちゃぐちゃに塗って仕上げてます。

●塗料
塗装にはプラモデル用の塗料が向いています。
リキッテクスなどでも大丈夫だと思いますが、試したことがありません。
塗料には大きく分けてラッカー系、水溶性・アクリル系、
エナメル系があります。それぞれに特徴、長所短所があります。
水溶性・アクリル系塗料は体への害も少なく、筆が水洗いできるので
オススメしたいところなのですが…乾燥がやや遅く、塗膜強度が
弱くて色が剥れやすい、色ムラが出易いなど弱点も多い印象です。

今回は普段使っているラッカー系を基本塗料として進めていきます。
乾燥が速く、塗膜も強く、発色も良くて筆ムラも出にくい。
価格も手ごろで色数も多く、入手し易いのもオススメポイントです。
一方で最大の短所はその強烈な臭いです。
特に溶剤はそのままシンナーなので、換気には充分に気を付けて
ください。中毒になる場合もあります。あと火気厳禁!!
●基本色の調色

モデルの大きな面積を占める基本色を作ります。
ラギアクルスなら背中面の青と、腹面のベージュの2色ですね。
基本色は最終的な完成品のイメージに大きく影響します。
その支配力は大きく、後からどんなに塗り足しても覆り難いです。
基本色が暗ければ、なんとなく暗い状態に仕上がります。
できるだけ慎重に探りながら、各色ひとビン分くらい用意します。
色が決まったら、以降は基本色をベースに塗装を進めていきます。
●塗装

今回は作例としてティガレックスの足を使います。
基本色を塗ったところです。ティガのイメージとは違うかも
知れませんが、見た目にわかりやすい色を選んでいます。
全体に基本色を塗ります。
ラギアの背中の青と、腹のベージュように色の境目になる部分には
両方の色を50%+50%で混ぜた色を塗ると馴染みます。
エアブラシだと楽なのですが、筆でところどころに基本色に
一見無関係の色を少しだけ混ぜた色を塗ってあげると
生物的な色の広がりが表現できます。汚くても大丈夫!
※作例はツヤツヤしてますが、ツヤは最後に消します。
基本色にフラットベース(つや消し剤)を混ぜてもOkです。

シャドウを塗ります。
影になる部分や、筋肉などが凹んだ部分に明度・彩度を低くした基本色を
塗りこみます。基本色に少し黒を混ぜると暗い基本色が作れます。
ちなみに自分はほとんど黒は使いません。作例では紺を混ぜています。
シャドウに黒を使うと全体に締まった印象になってかっこいいのですが、
アズキ色や紺など、濃い色を使うと仕上がりがまろやかになります。

ここでエナメル系塗料の登場です。
筆ムラが出にくく、塗料の伸びが良い。何より発色がとても良いです。
エナメル系はラッカーの塗膜に影響しないので、重ね塗りができます。
墨流しというテクニックがありまして…エナメル溶剤でしゃばしゃばに
溶いたエナメル塗料を、乾いたラッカー塗装の上から大胆に
塗ってしまいます。そうすると細かいモールドに塗料が流れ込んで
ディティールが一気に浮かび上がってきます。これは楽しいです!

目玉の周りにちょっと流し込んでやるだけで、ぐっといい顔に
なります。足や手の爪の付け根などなど、強調したい部分を中心に。
エナメル系塗料は乾燥が遅いので、半日~一日放置します。
塗装がはみ出した部分はエナメル溶剤を少し含ませたティッシュなどで
軽くふき取ると綺麗に消えます。

エナメル塗料が乾いたら、続いてはドライブラシです。
ラッカー系塗料を使います。
基本色に少し白などを混ぜて、明度・彩度の高い色を作ります。
中平筆などに少し塗料をつけて、紙などにしごくように擦りつけ、
余分な塗料を落とします。筆が乾燥してきたら準備OK。

パーツの表面を、筆で軽く優しく撫で付けるように色を乗せます。
色や筆がベタつくようなら乾燥が足りてないので、もう一度紙などで
しごきます。ディティールの凸部分に色を乗せる感覚です。

基本色+白少量+黄色少量のドライブラシをしました。
基本色をベースに、少しだけ無関係の色を足したものを
何色かドライブラシをすると深みと広がりが出ます。

基本色→墨流し→ドライブラシでなんだか上手く塗れた感じに。
基本色を塗った段階で「なんか汚い~」と感じても大丈夫です。
ぐちゃぐちゃでも、後の作業でぐっと締まります。

全ての塗装が完了したら、最後につや消しトップコートを
吹きます。表面を保護し、マットな仕上がりになります。
下の塗膜を侵食しない水性がオススメです。

怪獣塗装術を応用したモンハンの基本塗装はこんな感じです。(俺流だけど)
塗装の順番なのですが、自分はサーフェイサーで下地を塗ったら
ますは口の中を塗ってしまい、上あごと下あごは接着しちゃいます。
また、パーツとパーツの継ぎ目なのですが…自分は基本的に埋めてません。
一応目立たないようにパーツを分けてあるので、まあいいかと…。
どうしても埋める必要がある場合はスカルピーでちょちょいと成形して
オーブンで焼いた後に瞬間接着剤で強引に固めたりしてます。
オススメはエポキシパテですね。成形も容易で強度もありますし。

それでは簡単ではありましたが、組立塗装講座でした。
何か質問などありましたら、ここのコメント欄かTwitterなどで
お気軽にどうぞ!構えずに楽しんで塗ってやってくださいね!
講座ってほど偉そうなものでもないですが。
今回は塗装のテクニックについてです。
WF会場内で「エアブラシ持ってないし、こんなの塗れない!」
みたいな声を何度も耳にしたのですが、自分はほぼエアブラシは
使いません。何故って掃除とメンテナンスがめんどくさいから。

例えばWSCプレゼン作品の作り起こしベースは、近所のDIYで
適当な赤と青と緑の缶スプレーを買ってきて、ばばっと吹いて、
あとは筆でプラカラーをぐちゃぐちゃに塗って仕上げてます。

●塗料
塗装にはプラモデル用の塗料が向いています。
リキッテクスなどでも大丈夫だと思いますが、試したことがありません。
塗料には大きく分けてラッカー系、水溶性・アクリル系、
エナメル系があります。それぞれに特徴、長所短所があります。
水溶性・アクリル系塗料は体への害も少なく、筆が水洗いできるので
オススメしたいところなのですが…乾燥がやや遅く、塗膜強度が
弱くて色が剥れやすい、色ムラが出易いなど弱点も多い印象です。

今回は普段使っているラッカー系を基本塗料として進めていきます。
乾燥が速く、塗膜も強く、発色も良くて筆ムラも出にくい。
価格も手ごろで色数も多く、入手し易いのもオススメポイントです。
一方で最大の短所はその強烈な臭いです。
特に溶剤はそのままシンナーなので、換気には充分に気を付けて
ください。中毒になる場合もあります。あと火気厳禁!!
●基本色の調色

モデルの大きな面積を占める基本色を作ります。
ラギアクルスなら背中面の青と、腹面のベージュの2色ですね。
基本色は最終的な完成品のイメージに大きく影響します。
その支配力は大きく、後からどんなに塗り足しても覆り難いです。
基本色が暗ければ、なんとなく暗い状態に仕上がります。
できるだけ慎重に探りながら、各色ひとビン分くらい用意します。
色が決まったら、以降は基本色をベースに塗装を進めていきます。
●塗装

今回は作例としてティガレックスの足を使います。
基本色を塗ったところです。ティガのイメージとは違うかも
知れませんが、見た目にわかりやすい色を選んでいます。
全体に基本色を塗ります。
ラギアの背中の青と、腹のベージュように色の境目になる部分には
両方の色を50%+50%で混ぜた色を塗ると馴染みます。
エアブラシだと楽なのですが、筆でところどころに基本色に
一見無関係の色を少しだけ混ぜた色を塗ってあげると
生物的な色の広がりが表現できます。汚くても大丈夫!
※作例はツヤツヤしてますが、ツヤは最後に消します。
基本色にフラットベース(つや消し剤)を混ぜてもOkです。

シャドウを塗ります。
影になる部分や、筋肉などが凹んだ部分に明度・彩度を低くした基本色を
塗りこみます。基本色に少し黒を混ぜると暗い基本色が作れます。
ちなみに自分はほとんど黒は使いません。作例では紺を混ぜています。
シャドウに黒を使うと全体に締まった印象になってかっこいいのですが、
アズキ色や紺など、濃い色を使うと仕上がりがまろやかになります。

ここでエナメル系塗料の登場です。
筆ムラが出にくく、塗料の伸びが良い。何より発色がとても良いです。
エナメル系はラッカーの塗膜に影響しないので、重ね塗りができます。
墨流しというテクニックがありまして…エナメル溶剤でしゃばしゃばに
溶いたエナメル塗料を、乾いたラッカー塗装の上から大胆に
塗ってしまいます。そうすると細かいモールドに塗料が流れ込んで
ディティールが一気に浮かび上がってきます。これは楽しいです!

目玉の周りにちょっと流し込んでやるだけで、ぐっといい顔に
なります。足や手の爪の付け根などなど、強調したい部分を中心に。
エナメル系塗料は乾燥が遅いので、半日~一日放置します。
塗装がはみ出した部分はエナメル溶剤を少し含ませたティッシュなどで
軽くふき取ると綺麗に消えます。

エナメル塗料が乾いたら、続いてはドライブラシです。
ラッカー系塗料を使います。
基本色に少し白などを混ぜて、明度・彩度の高い色を作ります。
中平筆などに少し塗料をつけて、紙などにしごくように擦りつけ、
余分な塗料を落とします。筆が乾燥してきたら準備OK。

パーツの表面を、筆で軽く優しく撫で付けるように色を乗せます。
色や筆がベタつくようなら乾燥が足りてないので、もう一度紙などで
しごきます。ディティールの凸部分に色を乗せる感覚です。

基本色+白少量+黄色少量のドライブラシをしました。
基本色をベースに、少しだけ無関係の色を足したものを
何色かドライブラシをすると深みと広がりが出ます。

基本色→墨流し→ドライブラシでなんだか上手く塗れた感じに。
基本色を塗った段階で「なんか汚い~」と感じても大丈夫です。
ぐちゃぐちゃでも、後の作業でぐっと締まります。

全ての塗装が完了したら、最後につや消しトップコートを
吹きます。表面を保護し、マットな仕上がりになります。
下の塗膜を侵食しない水性がオススメです。

怪獣塗装術を応用したモンハンの基本塗装はこんな感じです。(俺流だけど)
塗装の順番なのですが、自分はサーフェイサーで下地を塗ったら
ますは口の中を塗ってしまい、上あごと下あごは接着しちゃいます。
また、パーツとパーツの継ぎ目なのですが…自分は基本的に埋めてません。
一応目立たないようにパーツを分けてあるので、まあいいかと…。
どうしても埋める必要がある場合はスカルピーでちょちょいと成形して
オーブンで焼いた後に瞬間接着剤で強引に固めたりしてます。
オススメはエポキシパテですね。成形も容易で強度もありますし。

それでは簡単ではありましたが、組立塗装講座でした。
何か質問などありましたら、ここのコメント欄かTwitterなどで
お気軽にどうぞ!構えずに楽しんで塗ってやってくださいね!
Posted by うらまっく at 15:18│Comments(2)
│フィギュア
この記事へのコメント
凄く参考になりましたヽ(〃∀〃)ノ
これからも応援しています!!!
これからも応援しています!!!
Posted by しゃかん at 2015年04月09日 12:19
ありがとうございます!
夏のWFに当選しましたので、
新作を発表できるよう頑張ります!
夏のWFに当選しましたので、
新作を発表できるよう頑張ります!
Posted by うらまっく at 2015年04月09日 16:15
at 2015年04月09日 16:15
 at 2015年04月09日 16:15
at 2015年04月09日 16:15